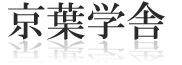民間教育機関の現状と突きつけられている課題
~日本の公教育とどのように関わろうとしているのか~
【学習塾百年の歴史・塾団体五十年史用原稿】
塾教育研究会(JKK)代表 皆倉宣之
目次:
《はじめに~問題の所在》
一.学習塾の現状
二、学習塾はなぜ存在しているのか
三.民間教育産業と公教育の市場化
四.学習塾から見えてくる日本の学校
五.学習塾(民間教育産業)の存在が引き起こしている課題
六.日本の教育をよりよくするために(一つの提言)
《おわりに》
《はじめに》
民間教育機関の一つであるわれわれ学習塾は、憲法が保障する営業の自由に基づいて自由な営業活動(主として教育活動)を行っている職種である。したがって、高邁な理想(例えば、日本の教育をよくするなどという)を高く掲げてその実現に情熱を傾ける義務と責任があるわけではない。そこにあるのは、市場経済原理に基づく明確な経済合理性の追求だけである。近年ますますその傾向が強まっているようにさえ思われる。それゆえに、現在する実態としての学習塾は語ることができても、日本の教育全体の中でどのような価値を付与できるかというような、その未来についてはなかなか語ることが困難である。
にもかかわらず、いま私がこのようなテーマを掲げたのは、我々が深く関わり何らかの影響を結果的に及ぼしている公教育との関係で、その関係の現状を確認し議論し、その中から何らかのよりよい方向へのヒントが見えてくれば、公教育と学習塾の双方にとって歓迎すべきことだと思われるからである。
その視点に立ってここでは、先ず、我々学習塾の現状を確認し、次に、我々のよって立つ根拠は何か、つまり学習塾はなぜ存在し得ているのか、その論拠は何かを探り、さらに、そこからわれわれ学習塾(民間教育機関)が今日の日本の公教育にどのような影響を及ぼしているか検証し、その功罪を論じてゆきたい。そうすることによって、そこから何を教訓として汲み取れるかを探り、最後に、学習塾の未来と展望へと繋げてゆければと思っている。
《注》本稿では場面に応じて塾、学習塾、予備校、民間教育産業、教育企業、私企業などと、様々な用語を使っているが、これは厳密な使い方ではない。強いてこれらの用語の区別をすれば、学習塾は主として小学生と中学生を対象とし、塾生2~30名の個人塾から数万人を擁する大手法人塾までを含み、学校とほぼ同一内容の授業を行って、学校の補習や中高受験のため需要を満たすことを目的としている。他方、予備校は主として大学受験の需要を満たすためのもので、高校生や浪人生がたいしょうである。これらに対して、民間教育産業、教育企業、私企業などは主として大手の通信添削事業者や教材会社、それに予備校などを含む概念である。もちろん塾を含めて公教育以外の機関で教育に携わるものは全て民間であるので、大手だけを指す場合が多いものの、塾を含む場合もある。
それゆえに、読者の皆さんは適宜文脈から意味を抽出して理解してもらいたい。要は「公」教育の部類に入るのか、「私」教育の部類に入るのかが明確になっていればそれでいいとの前提に立っている。
一.学習塾の現状
ここでは一般的な意味でのいわゆる学習塾を取り上げることにする。それゆえ、予備校や教材販売会社、通信添削会社、模擬テスト会社など、塾以外のいわゆる民間教育産業については別のものとして後で取り上げることにする。
さて、学習塾と言っても規模、存立形態、内容等さまざまであり、一口に把握することはできない。
1.学習塾の中身概観
規模による分類として、小規模塾(塾生200人未満)、中規模塾(塾生3000人未満)、大規模塾(塾生3000人以上)にわけられる。
存立の形態としては、個人立、会社立、上場企業会社立などがある。
指導の形態では、集団指導型と個別指導型、家庭教師派遣型、通信添削型などがあり、最近は個別指導型の増加が著しい。また、通信添削型は巨大な民間教育産業3社がほぼ独占している。
指導の方法については、人が教えると言う従来のスタイルだけでなく、最近はコンピュータ機器などを使っての機械による教授法が増加している。
授業内容に関しては、学校の教科書の予習・復習であり(ダブルスクール)、ただ受験を前提としているかどうかで難易度の違いがあるだけである。それゆえに、一口でいえば授業内容の画一化がますます進行しつつある。教育機器の進化発達がそれを助長している。
つまり、公教育とは異なる塾独自の教育(塾教育)は行われていないのである。全てが受験勉強に収斂される日本の教育風土の結果であろう。
2.変化する学習塾~社会の変化と教育改革の流れの中で
1)1984年、当時の中曽根康弘首相の主導で「臨時教育審議会」が設置され、そこで「教育の自由化」が議論され、「個性の重視・育成」がスローガンに掲げられ、「教育の個性化」が提案された。これを契機に1989年から2000年にかけての10年間は、参考資料に掲げたとおり、経済界のすさまじい反応が起きた時期であった。そのキーワードは、「個性」・「自由」・「選択」・「責任」である。これが今日の日本の教育政策の根底をなしているといってよい。
特に衝撃を与えたのが1995年に経済同友会が打ち出した「学校から『合校(がっこう)』へ」構想であり、さらに2000年1月に「21世紀日本の構想」懇談会(小渕首相の諮問機関)の「現在の義務教育の教科内容を5分の3にまで圧縮し、義務教育週3日制を目指す」という提言であった。ここには「提案したいのは、週7日のうちの半分以上、すなわち少年期の半分以上を生徒と親の自由選択、自己責任に委ねて見ようということである。」とある。
2)ただし、これらの経緯を理解するにはかなりの労力を必要とする。
すなわち、先ず「個性の尊重」というキャッチフレーズは、これまで批判されてきた詰め込み教育とか画一的教育(これが落ちこぼしを生み、いじめを発生させる源とされてきた)という傾向に対する対応策という風に受け止められた。そして、その具体策として「学校週5日制」への移行と「教科内容の削減」が打ち出され、いわゆる「ゆとり教育」と呼ばれるようになった。
これらは当初は好意的に受け止められていたが、やがて二つの潮流に反撃されることになった。一つは、ゆとり教育は学力の低下を招くという批判で、当初は理系の学者が中心となっていたが、やがて小中生を持つ親たちの不安が広がり、そこから学習塾通いの増加と私立学校を受験するという流れが急速にできていった。と同時に、学習塾と私学は一体になって「公立学校」バッシングを始めた。
もう一つは、理論的な側面が高いのであるが、「個性の尊重」というものの中身の実態についてである。「できない」のも個性だという有名な言葉が生まれたりしたが、このことが一端を明確に表現しているように、これは国家の公教育からの縮小を意味し、国家は教育に対しては最低限の関与に留め(教育予算の削減が狙い)、後は国民の自己責任(教育の自由化・規制緩和を通じての民間教育産業の育成)でどうぞというものである(新自由主義の思想→結果としての教育の私事化の助長)。
具体的に出されたのが先に述べた「学校週5日制」であり「教科内容の削減」であった。
その結果生じてきたのが所得格差・階層格差に伴う学力の二極化である。すなわち、経済に余裕のある家庭や文化度の高い家庭は、ゆとりの時間を親子で上手に使うことができる。お稽古事や塾通い、図書館や美術館や博物館などへ行ける。しかし、それらの余裕のない家庭の子どもたちは野放し状態にされ、教育的環境からは程遠い状態におかれ、学力の低下へと繋がってゆくことになる。
この流れは、とうとうPISAの結果という思わぬ伏兵によって、大打撃をうけることになり、いままでの「ゆとり」をもって教育の質を上げると言う幻想は吹っ飛んでしまった。その解決策が「全国学力テスト」の復活であり、学習指導要領の見直しである。相も変らぬ目先の効果だけを狙う政策である。なぜなら、学力格差が家庭の経済格差に起因するところが大であるという現実を踏まえると、「相対的貧困率」が09年時点で16.0%でり(OECDの08年報告書では、加盟30カ国の平均は10.6%)、「ひとり親」家庭の貧困率に至っては07年時点で54・3%(OECD加盟30カ国でも「最下位」の水準)という状態の下での学力の向上策は、先ずは国の教育費の増大を目指すべきだからである(教育予算のGDPに占める割合は、OECD平均→5.0%であるのに対し、日本→3.5%に過ぎない)。
3)国家が絡む教育政策とは別に、教育に、そして学習塾に大きな変化をもたらしてきた要因に、「情報革命」と「少子化」の進展がある。特に、臨教審以後の25年間の変化は著しく、インターネットと携帯電話の急速な発達はその最たるものである。
近代は人間を自由にし個人を解放した。社会や家(族)からの束縛を徐々に取り払ってきた。そこに現れるのは個人化、個別化の進展である。パソコンの世界では社会との接触が不要となり、家族全員が持つようになったケータイは家族のまとまりを解体してゆく。あくなき個別化はあらゆる物を私事化してゆく。ここに本来は消費の主体は経済力のある大人であったはずなのに、経済力のない子どもまでもが消費の主体に組み込まれてゆく契機が生まれ、すかさず商品の売り手たちはそこを目指して大攻勢をかけてくる。
このようにして、教育の自由化と相まって、教育までもが商品化され、子どもたちは教育の消費者とされ、教育における「公」の側面が薄れて、「私」の側面→私事化が進行してゆくことになる。
このような流れと、私学ブーム、そして学習塾通いは決して無縁ではない。
【参考資料】1989年~2000年における経済界の教育改革提言(作成者・皆倉)
ア)89年 12月 経済同友会「新しい個の育成」
イ)91年 6月 経済同友会「『選択の自由』を目指して」
ウ)93年 7月 東京商工会議所「わが国企業に求められる人材と今後の教育のあり方」
エ)93年 7月 経団連「新しい人間尊重の時代における構造改革と教育のあり方について」
オ)94年 1月 日経連・労働問題研究委員会「深刻化する長期不況と雇用維持にむけての労使の対応」
カ)94年 4月 経済同友会「大衆化時代の新しい大学像を求めて―学ぶ意欲と能力に応える改革を」
キ)94年 4月 関西経済同友会「地球時代の新世紀を拓く人づくりを目指して―教育改革への提言」
ク)94年 8月 日経連「新時代の『日本的経営』ー挑戦すべき方向とその具体策」※ス)参照
【この報告は、きわめて注目すべき発言をしている。すなわち、今後予想される労働力の流動化を雇用形態の多様化としてとらえ、労働力を雇用形態別に、
①長期蓄積能力活用型(企業の核となる継続雇用グループ)
②高度専門能力活用グループ(流動性をもった専門職グループ)
③柔軟雇用型(契約社員・パート等の不安定労働者グループ)
の三つの類型に分けて構想している。
このような分類に基づく労働力流動化政策は、労働力の新たな種別化・選別化であり、雇用形態の多様化や複線型人事管理をよびおこし、それだけ生涯学習の要請を高めることになろう】
ケ)94年 9月 東京商工会議所「新しい高等教育のあり方についての提言―自主開発型人材の育成と複線型高等教育の構築に向けて」
コ)95年 1月 日経連・労働問題研究委員会「日本経済の再活性化と経営者、労使の課題」
サ)95年 4月 経済同友会「学校から『合校』へ」
シ)95年 4月 日経連「新時代に挑戦する大学教育と企業の対応」
ス)95年 5月 日経連「新時代の『日本的経営』ー挑戦すべき方向とその具体策」
※ク)の本答申
セ)96年 3月 経団連「創造的な人間の育成に向けて~求められる教育改革と企業の行動~」
ソ)97年 2月 日経連「グローバル社会に貢献する人材の育成を」
タ)97年 3月 経済同友会「『学働遊合』のすすめ」
チ)98年 4月 経済企画庁経済研究所・教育経済研究会編 「エコノミストによる教育改革への提言」 【この提言は、政府与党の教育改革への提言の方向を、補完・側面支援することを明言しているめずらしい書物である。行政官庁の発言そのものか?】
ツ)98年 7月 社会経済生産性本部・社会政策特別委員会 中間報告「選択・責任・連帯の改革~学校の機能回復をめざして」
テ)99年 4月 経済同友会「創造的科学技術開発を担う人材育成への提言―『教える教育』から『学ぶ教育』への転換―
ト)2000 1月 「21世紀日本の構想」懇談会:第5章「日本人の未来」。
3.激化する学習塾間のシェア争い
少子化はあらゆる業界に暗い影を及ぼしているが、塾業界にとっても同じである。当然に子どもの獲得(塾生確保)を巡って激しいシェア争いが起きる。それは、初めのうちは塾間の生徒を巡る争いである。授業料を下げたり、時間数を増やしたり、少人数制をうたったり、最近は新しく進出する地での講習会無料や授業料の激安作戦というものまででてきている。
こういう状況の中で、大きい塾が小さい塾のシェアを奪い、中小塾の倒産や撤退が増えている。これは、塾の評価が以前のように地域に密着して地域の子どもが中心に集まる塾といったイメージが崩れ、宣伝チラシの回数や設備の具合といった表面的な要素に左右される傾向があること、さらには交通の便がよくなり駅周辺の塾への接近が容易になったことなどによるものと思われる。小さい塾が多く集まって個性のある塾長が多様な教育を行っていたころに比べると、それらが大手に取って代わられることにより塾教育が画一的なものになってゆきつつある。
が、それだけでは収まらなくなって、ついには大企業並みの他塾の買収・合併へと発展する。そこには、大手の予備校や民間教育産業と称せられる巨大な組織が絡んでいる。もうここには、旧来の牧歌的な塾のイメージは存在しない。そこにあるのは、教育をサービス=商品と捉え、子どもたちを顧客と見る経済の論理のみであり、「公」教育という概念はどこかへ押しやられている世界である。
4.私立学校と学習塾~もちつもたれつの関係・一致する利害を生かす~
1)先に少し触れたが、2000年代に入ってから私学ブームが起きている。その引き金は90年代に始まった教育改革(いわゆる「ゆとり」教育)である。
このままでは分数もできない大学生が生まれるというセンセーショナルな叫びと同時に、「公立学校へわが子を通わせていたらダメになる」といった親たちの公立学校への不安感と不信感は相当なものとなり、だから私立学校へ、そのためには塾へ、という構図が強固になっていった。
少子化の進展は、塾にとっても私学にとっても生死を左右する重大事象であるがゆえに、その生き残り策を求めていた矢先の教育改革の失策であった。これを機に、従来にも増して塾と私学との連携は強まり、一体となって公立学校バッシングへと走ることになった。これはいわば、塾教育や私学教育に公立学校とは明確に異なる優れた教育実践があるからと言うわけではなく、親たちの公立学校への不安感と不信感といういわば敵失による反射的利益にほかならない。このことを特に私学は肝に銘じておくべきだろう。
2)さて、塾と私学の関係において、この10年間で大きな問題が浮上している。それは模擬テストで合否判定を行う大手塾の私学への影響力の増大である。少子化と経済不況とで私学の半数近くが定員割れを起こしている。私学経営はいたって苦しい現実がある。それゆえに、私学としては、何としてでも生徒が欲しい。その際頼れるのは塾のみである。
このような状況から生じてくる私学の落とし穴は、生徒獲得に乗じた大手塾の横暴な振る舞いである。それには色々な手段があるようだが、合格点以下の成績の振るわない塾生(例えば5人)と成績上位の塾生(1名)との抱き合わせ取引である。また、模擬テストにおける各学校の偏差値の操作という方法もある(ある学校の実際の合格偏差値は50なのに、55とするといった具合に)。これらにまつわる逸話は事欠かないが、もう一つ例を挙げると、私立中学受験に絶大な影響力を持っている塾のトップの子息の結婚式には、2000人近い私学関係者が集まったそうだ(祝儀がどれほど集まったことかと余計な心配をしてしまう)。これだけの人数が集まると言うことは、塾から案内状が私学へ届けられているに違いない。私学としては全く関係のない個人の式典に参加するかしないかは自由であるはずだが、そこには目に見えない圧力が見え隠れしている。一種の踏み絵である。
ここまで大手進学塾の力は巨大化しているのである。塾と私学の蜜月は両刃の剣でもある。
さて、このような大手塾優位が続けば行き着くところは、私学の経営支配である。先ずは入試日への介入から始まり、授業科目への口出し、そして人事に目をつけ、ついにはトップに息のかかった民間からの者を送り込むということになる。
これはゆゆしきことで、私学と言えども公教育の一貫を担っているわけであり、公教育の崩壊を意味する。このような形でも、公教育の縮小が進んでいると言えよう。
なお、校内塾という形態も問題となる。私立学校が塾や予備校に委託して、自校の生徒の補習や受験勉強を校内の施設(または学校近くの塾)を使って行わせる形態の塾である。
ここにも公教育たる私学が民間教育産業と一体化するという公教育の縮小化現象が見受けられる。
5.行政(教育委員会・公立学校)の変身と学習塾
1)東京都杉並区の区立和田中学校が、学校の教室を使って夜間に大手塾の授業を行うという出来事は、塾と言う民間企業が公立学校内で営利活動を行うという前代未聞の珍事ということで、日本国中の話題を呼んだ(いわゆる「夜スぺ」問題)。当初東京都教育委員会の担当部署は、旧来のまともな学習塾観でそれを好ましくないとしていた。しかし、首脳部の意向を汲んでOKとした。
この流れは、他の区や市町村でも学校が休みの土曜日を使って高校では予備校に、小中学校では学習塾に委託して進学準備の授業や補習授業を行うという形態へと発展している。
また、貧困世帯の多い地域では、自治体が低所得家庭の生徒に塾代を補助するという方式も出現している。
さらには、東北の人口が少なく周囲に学習塾のない村などが、学力アップのために村費で塾を誘致したり、直営の塾を開設し塾から講師を派遣してもらったりする事例も見られる。
2)このような現場の実態をどのように総括したらよいのだろうか。先ず取り上げられるべきは、行政(文科省や地方公共団体)と塾の関係の変化である。80年代までの塾撲滅論から、無視、放任、そして2000年ごろからは連携へと行政は舵をきってきていることである。これは、先に2.で述べた経済界の動向に沿った変化と言うことができる。すなわち、教育の自由化の推進および教育の多様化という名の公教育の縮小、逆から見れば公教育への民間企業の参入の容認・拡大という路線である。
さらには、その背景にはますます進む個人化、個別化の中での親たち、つまり世論の教育を「私事」とする傾向の強まりがある。
これらをまとめると、学習塾・予備校(民間企業)を取り込む行政と、行政に取り込まれる学習塾・予備校という構図があり、公教育が縮小されながら「公」と「私」の境界が極めて曖昧化してゆくという現象が起きているということである。
6.マスコミの変身と塾
先に行政の変身ということを論じてきたが、もう一つ変身してきたものがある。それはマスコミである。公器といわれていたマスコミの力が弱まっていることは、新聞においては広告主と購読者への配慮からであり、テレビにおいては広告主と視聴率への配慮からである。権力に立ち向かうというよりは、経済的利益を優先するという風潮が伺える。
このような状況の中でマスコミは、世論の塾容認の流れ(それは積極的というよりは、公立学校への不満の表れという消極的なものである)、および行政の塾容認への変身という流れを受けて、社会の風潮と軌を一にするほうを選択しているといってよい。
ここで欠落しているものは何か。それは教育を論じながら公教育とは?という問いの欠落である。表面的な世間の話題となるような、例えば1月から2月へかけての私立中学受験期になれば、塾での受験特訓を面白おかしく報道するだけで、その背後に隠された多くの問題点をえぐるという姿勢は、もはや見られない。娯楽番組と同じ感覚だといってよい。受験情報は話題に取り上げるが、公立高校の課題集積高(教育困難高)などのルポはほとんど姿を消している。
最近、塾や予備校や教育企業からの新聞広告が目立つ(テレビでも大手は同様)。その収入の広告費全体に占める割合は相当なものだと思われる。これに小学生新聞が加わる。受験産業の広告で埋め尽くされんばかりである。広告主からの反感を買うような記事は書けなくなっているのだろうか。
二.学習塾はなぜ存在しているのか
1.学習塾を論じる際に先ず一番先に押さえておかなければならないことは、世界的に見て学習塾が栄えている国、言い換えれば国家の教育や社会に大きな影響を与えている国は、日本、韓国、香港、台湾と言った東アジア圏の国々・地域であり(これらの国々・地域には、儒教圏であることと、米英にかつて占領されたことがあるという共通する興味深い点が存在する)、ヨーロッパはもとより他の諸国にも例をみないということである。そういう意味からも、なぜその国で学習塾が繁栄しているのかの理由を探ることは、その国の公教育や社会の在りようを探る重要なポイントとなる。
2.学習塾を成り立たせている要因は、一言でいえば親や子どもたちのニーズである。そのニーズが消滅すれば塾は成り立たなくなり、存在し得なくなる。
では、ニーズとは何か、ニーズの中身とは何かが問題となる。それを端的に指摘すれば、親たちの公教育(公立学校)への不安と不満である。塾が不安産業であるともいわれる所以である。では、その公立学校への不安と不満の具体的中身は何だろうか。
それは一口で言えば、学力への不安・不満である(もちろん、公立学校批判には、いじめが多い、学級崩壊が起きている、面倒見が悪い等々の理由もあるが、塾へ直結する理由はやはり学力低下への不安が第1だろう)。ところが、学力への不安・不満といってもそこには質の異なる二つの流れが存在する。一つは、もっと高い学力を要求する流れ(特に私立中学受験)であり、他の一つは、国の教育政策の欠陥に起因する基礎学力の定着を求める流れである。前者の層は中高受験で上位校志望層であり、いわゆる大手進学塾へと流れ、後者の層はその他の塾へと流れる。
3.先ず前者の学力であるが、わが国の中高大受験を巡る熾烈な競争に起因する。東大を頂点とする受験競争は、必然的に高校受験における学力競争を引き起こし、さらには私立の中高一貫校が断然有利だということになれば、中学受験が過熱するのは必然である。特に、私立の中高一貫校が大学の難関校を突破するのに有利である現状からは、高校入試よりも中学入試のほうが受験競争においては熾烈である。その際、公立小学校の受験への関与は皆無だから、頼れるのは唯一つ、学習塾だけである。かくて、有名中学受験という特殊な場面においては、学習塾とは切っても切れない強固な「絆」、言い換えれば強固な「ニーズ」が生まれることになる。
ところが、この受験競争というのは、大学入試制度のみならず大学を卒業してからの就職の現実、さらには大企業における人事の在り様といった日本の社会構造と絡む大きな問題を含むものだけに、一朝一夕に解決できるものではない。それゆえに、この受験競争が続く限り予備校や受験塾も安定した存続が保証されることになる。
4.後者の基礎学力への不安・不満は、私立中学校を目指す約3割の層(この層はもうとっくに公立学校を相手にしていない)を差し引いた7割の層が直面する問題であるだけに、国の教育政策の欠陥(問題点)を炙り出しているといえよう。したがって、ここでは国のこれまでの教育政策の問題点、すなわち、ここ25年にわたる公教育の縮小化=私事化を改めて、公教育の充実・拡大へと方向を転換しなければならない。その際に先ず行うべきは教育予算の充実・拡大である。教員を増やし、臨時職員を無くし正職員にし、授業についてこられない生徒のための補習や土曜授業を、塾など外部に委託することなく、正規の授業として取り組むべきである。基礎学力への不安・不満こそは、目下の政治的緊急課題でもある。これを解決しない限り、どんな教育改革を口にしても、日本の教育の再生はあり得ないと言っても過言ではないだろう。
ただし、これが解決されれば、塾へのニーズは半減するだろう。すなわち、高校受験(主として公立高校)を控えた中3生は別として、少なくとも小学生からの塾通いは減ってゆくだろう。
5.以上みてきたことを裏返して考えると、学習塾は現象としては公教育(公立学校)への親たちの不満や不安を解消することを通じて、また一時的緊急の避難場所として、結果的にではあれ社会的、公共的(公益的)な役割を担っているといえるのではないか。表現を変えれば、公教育と塾教育とは本来は全く別個のものであるはずだが(例えば、指導要領の縛りがあるかどうか、教員免許は必要かどうかなど)、現状は両者は車の両輪の様相を呈し、塾が公教育を補完している。
このことは、「学校と塾は合わせ鏡のような存在である」とも、また、「塾は学校の補完機能をなしている」とか、「ダブルスクール」だとも言われる所以であろう。それゆえに、公教育(公立学校)への不満が継続する限り、言い換えれば公教育(公立学校)の改革が成功しない限り、学習塾は継続を保障された存在となっていると言ってよい。
だが、そうなると先ほどから触れてきた公教育と私教育(民間教育)との融合ないしは境界線の曖昧化、言い換えれば公教育の縮小化という現象を追認することになり、このことは公教育制度を前提としているわが国の教育政策の根幹を揺るがすことになり、国の教育政策の失敗を決定付けることを意味し、その責任が問われることになる。
三.民間教育産業と公教育の市場化
これまで学習塾を中心として公教育との関連を述べてきたが、一般国民にはそれほど気づかれていない塾以外の民間教育産業と公教育との問題点を探ってゆきたい。
1.3.激化する学習塾間のシェア争いの項で触れたように、中堅塾や大手塾を巡っての巨大な予備校や民間教育産業によるS&Bは、年々激しくなっている。東進ハイスクールによる四谷大塚、代ゼミによるサピックスの買収などがその代表例である。
ではいまなぜこのような買収・合併が起きているのだろうか。それは、少子化による塾生の減少を食い止めるためである。とはいっても、なぜ高校生や浪人生を相手の予備校が小中学生相手の塾を傘下に収めるのか。それは、小中高生の一貫した支配を狙っているからである。小学生を塾で押さえれば、中高と大学受験までの流れを予備校が押さえることができるからである。ここには、小学生をも自分の予備校で青田買いしたいというしたたかな計算がある。
2.次に、予備校による大学への進出である。カリキュラムの作成を手伝ったり、講師を派遣して授業に入り込んだり、極め付きは大学入試問題の作成を引き受けるといったことまで行っている。
だからといって、予備校が悪いわけではない。そのようなニーズを作り出している大学の側こそ糾弾されるべきである。なぜなら、多額の補助金を国からもらいながら、大学設置の目的を自ら実現できない無能力こそ責められるべきだからである。
かくして、公教育であるべき大学へも民間教育産業が入り込み、私教育が公教育を駆逐してゆく現象が生じている。
3.民間教育産業といっても、予備校以外ではベネッセ、学研、Z会、内田洋行などが挙げられるが、これらは予備校や塾のように直接生徒たちを教えるというスタイルではなく、通信添削や教育機器の販売といった分野でシェアを伸ばしている。中でも、ベネッセと内田洋行の名を高めたのは、全国学力テストの採点業務をこの2社が請け負ったことである。
これらの中でも、その規模と質の両面において圧倒的に力の大きいのがベネッセである。
「進研ゼミ」という添削指導は、全国津々浦々の小中高生にまで行き渡っている。それに要する費用が塾や予備校の授業料の数分の1で足りるというメリットが、人気を呼んでいる秘密の一つと言われているが、そこにはわが国の教育に投資する自己負担の高さを緩和するという効果も見受けられるのではないだろうか。塾・予備校&ベネッセという時代がくるかも知れない。
4.ところで、ベネッセといえば先に触れた「全国学力テスト」を受託することにおいて、公教育への参入の大きな足がかかりを掴んだと言われている。それは、テストの採点およびその分析、そしてテストに関連する生徒状況調査等のデータを独占できたからである。これらのデータの中には日本全国の小6生と中3生の個人情報が詰まっており、それを毎年繰り返せば高校生や大学生までの一貫した情報を手に入れることができ、それを使っての諸々の事業が可能となり得る。現に模擬テスト問題を作成し全国各地の学校現場へ売り込んでいるとの情報もある。
このことは、民間企業が国の重要な教育の中身にまで参入しているということであり、市場化を通じた公教育の縮小ないしは民営化へと移行することを意味している。
以上のほかに、ベネッセは高校での大学受験指導で圧倒的な強さを見せている。開成や灘高といった上位校は別だろうが、その他の中堅校を中心とした大多数の日本の公私立高校へ入り込んでいる。その要因は、高校内での模擬試験のデータを利用したその後の手厚いアフターケアにある。それが実施した高校側の信頼を獲得している。通信添削と併用した模試は、高校と言う公的教育機関を利用しているだけに、生徒たちへの影響も大きい。
模試と同時に行われる生徒個人への諸々のアンケート調査は、個人情報満載である。生徒たちの個人情報が私企業によって公教育の現場で堂々と収集されるということ自体が、許されることではあるまい。これは予備校の学校内での模試においても同様だ。
問題はそれにとどまらず、高校の教師たちが全面的に進学指導をベネッセに頼っていることである。自校で模擬テストを行い、進路指導の教師がそれに沿って進学指導をするという風景は全く姿を消し、教師(高校)は業者の作成したデータをそのままに生徒へ伝える単なる伝達機関へと化してる。このような実態が全国規模で行われているという現実は、
高校が民間企業による利益追求の場となっていることを意味し、許されるべきことではないだろう。これはもはや公教育ではなく半官半民教育だと言っていいのではないか。公教育の縮小と解体はどんどん進んでいるように思われる。
もちろんこのような現実は、ベネッセや予備校が悪いのではなく、その責任は高校教育を受験競争のなすがままに任せてしまっている高校現場ならびにそれを推奨している教育委員会にあると言ってよい。受験を意識した教育を否定はしないが、そうであるならせめて高校が自前で受験指導も責任を持って行うべきだと考えるからである。
四.学習塾から見えてくる日本の学校
1.わが国の学校のうち、小中学校自体はそれほど受験競争に巻き込まれていない。つまり、小中学校が受験のための授業や対策を採るようなことはない。もっとも、中学において中3生の高校受験を前にして、進路指導という名目の下で受験に関する情報を与えたり、業者の模擬テストを導入したりしてはいる。だが、進学指導や模擬テストに関しては、生徒や保護者にとっては、塾などの学校外の方が信頼性が高いというのが現実である。
なお、全国学力テストの結果を重大視する都道府県においては、学校を挙げて成績を上げようと奮闘するところも出てきている。
2.問題は高校である。大学入試の合格実績という画一的物差しで高校の優劣を決めると言うわが国の社会通念の下では、中学入試で選抜し中高6ヵ年を通じた受験を念頭に置いた授業を行っている私立の中高一貫校の側に軍配が上がるのは当然のことである。そのことを中学入試においてことさらに強調し、公立高校では難関大学入試は突破できないという宣伝文句は、世の親たちへの強烈なメッセージとなってゆく。それはやがて、政治問題化する。「おらが県の東大合格者数は何でこんなに低いんだ」といった議論が、九州の県議会で取り沙汰されたのは有名な話であるが、これは一定の真実を突いている。なぜなら、県民の立場に立てば、多額の公費を費やしているのに公立高校の合格実績があまりに低いのは、学校現場が弛んでいるのではないかという不満がでてくるのは当然のことだろう。
公立の復権はいわば都道府県教委の合言葉なのである。
3.そこでトップバッターとして登場したのが豪腕知事をいただく東京都教育委員会である。都教委は、特色ある学校づくりの一環として進学対策を充実させるため、平成13年9月に「進学指導重点校」として、日比谷高校、戸山高校、西高校、八王子東高校の4校を指定し、その後も次々と進学対策を打ち出している。
その際、これまでタブーとされてきた予備校の活用がおおっぴらに謳われている。すなわち、つい最近に決定された「都立高等学校学力向上開拓推進事業について」によると、
外部機関による進学指導診断を行うとして、その目的を「都立高校における進学指導のマネージメントの定着を図るため、進学指導に関する専門的な知識を有し、学校に対して進学実績の向上に資するアドバイスを行うことのできる進学指導アドバイザーを学校に派遣し、進学指導診断を実施する、としている。具体的には、
①「進学実績向上のための経営戦略の診断」として、校長、副校長を対象として、内容として学校が目指す進学指導のあり方、進学実績向上に向けた具体的な取組及び進学実績の状況等について診断及びアドバイスを行う、
②次に、進路指導部の構成員、学年進路担当者を対象とした「進学指導体制の診断」を行い、
③最後に、「指導力向上に向けた教科指導の診断」として、国語、数学、英語の各教科それぞれ2名の教員と、地歴公民及び理科のうち1教科について2名の教員を対象として、教科の指導方法、学力の最終到達目標達成に向けた授業の妥当性、授業の評価及び大学受験への動機付け等について診断及びアドバイスを行うことになっている。
ところで、都教委がいうところの進学指導アドバイザーとは一体誰だろうか。なんと、河合塾、駿台予備学校、ベネッセコーポレーション、代々木ゼミナール4社の外部講師と明記されている。日本の教育を実質的に牛耳じっているとも言われている最強の民間教育産業である。
しかしながら、ここまで民間教育産業に頼りきってしまうのは、公教育の放棄ではないのかと不安になる。受験に気をもむ親たちの気持ちを汲んでのことだろうが、一方では私学を意識していることも隠せない。そうなると、公私双方の受験競争がますます激化し、それに逆比例してますます本来の高校教育は希薄化され、その存在意義はなくなってゆくだろう。
そういう意味では、高校をめぐる民間教育の関与は予備校が主役となり、一般的意味での塾の関与は弱いといえる。
4.かくして、公立を巻き込んでのますますの一流大学への受験競争は、高校受験、そして中学への受験競争の激化をまねいてきている。
これらの流れを直視すると、公立高校の民営化路線と同時に、私学化現象が生じているということではないだろうか。つまり、公立と私立の設立の理念或いは建学の精神などといったものはとっくに消えてなくなり、残るのは大学合格実績だけという状態である。それゆえに、どの高校を選択するかという受験する側の基準はと言えば、ただただ大学合格実績のみということになる。
5.一方において、このような進学競争とは全く無縁な高校(特に公立)が存在する。いわゆる教育困難校(課題集積校)といわれる高校の存在である。
このような実態が生じた背景には、高校入試における偏差値による輪切りと、バブル崩壊時から急速に起きてきた所得格差(勝ち組と負け組みという分類もある)の増加がある。
そこでは、家庭の経済力が教育環境の優劣を規定し、それが即学力と結びつている。そこから学力の2極化が始まる。2極の下層から上層への対流は、家庭の経済力においても学力においても、もはや極めて困難化しつつある。
このようなことは、公教育の現場(高校現場)にも大きく影響を及ぼしている。例えば、エアコン設置率、授業料免除率、退学率、部活加入率etc.などから見えてくる学校における格差の存在と、それらが教育環境という側面から生徒たちに及ぼす負の側面である。
千葉県の場合、エアコンの設置については県は何も対応していない。したがって、学校ごとに独自に親たちが金を出し合ってエアコンを設置している(月に1000円ぐらいの負担になるだろうか?)。しかし、その負担に耐えられない家庭がある。そういう家庭の子どもが多く通っている高校では、当然のことながらエアコンは設置はできない。かくて、空調の効いた涼しい教室で勉強できる生徒と、温室のような教室で勉強している生徒との
間の学力は開くばかりである。
ところで、このエアコン設置率からみえてくる驚くべき結果がある。それは、エアコンを設置している高校と設置していない高校との双方を高校入試時の受験偏差値のグラフ上に重ねてみると、偏差値50ぐらいから上位の高校にはエアコンがあり、それより下位の高校にはないという事実である。この現象は、他の授業料免除率、退学率、部活加入率ともほぼ一致する。エアコンがない、授業料免除者が多い、退学者が多い、部活加入者が少ないという事実は何を物語っているのだろうか。
このような貧困家庭層の増大は、高校での授業料免除の急増、公立小中学校における就学援助の受給率の急増となって表面化しているが、そのほかにも目立たないけれどもいろいろな形をとってその困難な状況が起きている。例えば、親や周囲に進路相談のできる人がいないとか、高卒で就職するには免許が必須であるが、教習所へ通う金がないので免許が取得できずに就職ができないとか、遠くまで会社面接に行くには交通費が必要となるがそれがないために就職できない、といった嘆きなどである。ここには、「私」と「公」の双方から見捨てられた生徒たちがいる(ここでは、教育と福祉がせめぎあっているといえる)。
そして、彼らには塾も予備校も通信添削も無縁なのである。ここには、民間教育産業の限界とその本質があらわになっており、公教育の充実の必要性が逆照射されてくる。
五.学習塾(民間教育産業)の存在が引き起こしている課題
以前は学習塾は公教育の阻害者として、或いは児童生徒の過度の塾通いが引き起こすであろう健康への危惧から、行政や学校、マスコミから非難の対象であったが、いまやその風向きはほぼ変わった。したがって、自由主義経済の下での活動には原則として制約はなく、それゆえに負の側面も直接には表面化していないようだ。しかしながら、社会が学習塾を容認すればするほどそれに伴う責任が間接的には強まることを自覚すべきである。
では、いかなる課題があるだろうか。以下この問題を取り上げてみたい。
1.先ずは、実態としての学校と塾という「ダブルスクール」の持つ意味についてである。私が所属する塾教育研究会(JKK)は、昨年5月にカナダのUBCアジア研究所・副所長,准教授のジュリアン・ディルケス氏をお招きして「外国の教育社会学者が見た日本の学習塾」というシンポジウムを行った。このテーマは教育学者やマスコミ関係者にも大きなインパクトを与えたが、氏の5年間に及ぶ日本の塾の実態は「学校と何ら変わらない」であった。すなわち、昼間学校で勉強したことを夜塾でまた勉強する、というのが塾の実態だということである。
氏が日本の塾研究をしようとしたその目的は(カナダ政府の公的資金援助を得てまで)、日本の驚くべき経済成長の背景には必ずや教育の力があるに違いないく、その教育の力を形成しているのが公教育(学校)と共存していながら、しかしそれとは異なる多様性に富んだ「塾教育」ではないのか、それが経済成長の一端を担っているに違いない、と想像したからである。
ところが、関西から東北までの50余の塾を丹念に回った結果得た結論が、先に述べた学校と何ら変わらない教育であり、その教育内容は画一的であるということでであった。
2.ここからみえてくる課題は、先ず、生徒(=塾生)を中心にして考えたらどのようになるかと言うことである。この課題は、塾の存在に慣れっこになっているわれわれ日本人からはなかなか提起されないが、外国人からは度々指摘されるものである。
一つは、なぜ同じ生徒が学校と塾の双方に通って同じ内容の授業を受けなければならないのか、という疑問である。つまりダブルスクールが生徒たちに与えているメリットとデメリットについて、何ならかの説明或いは根拠を提起すべきではなのかということである。ニーズがあるからといえばそれまでだが、第1の答弁者は文部当局だろうが、塾が教育者を自認するのであれば第2の答弁者としてでていくべきだろう。
もう一つは、ダブルスクールを容認するのであれば、なぜ塾と学校が連携しないのかという疑問が投げかけられている。塾や学校の立場ではなく、生徒の立場から考えた場合、両者の連携はより優れた教育効果をもたらすと思われる。双方の課題である。
3.次に、塾を中心に考えた場合どうなるかである。先ほどから述べてきたように、塾へのニーズの主たる理由が親たちの公教育への不安と不満であるとすれば、塾は公教育に対してどのような姿勢を持つべきか、という点である。このままの方が塾にとって利益があるから今のままにしておいた方がいいという考えに立つのか、いや塾には公教育とは異なる独自の塾教育が存在しそれを追求するのだという考えに立つのか、という問いである。
しかし、後者は理想的ではあるが、現在のニーズ論からすれば、成り立ち得ない考えに違いない。それは、経済的利益を得るために年々株式会社化してゆく塾が増えていることや、塾は公教育の隙間に入り込み利益を追求する「隙間教育産業」であるという性格からも導かれる結論である。
とはいえ、ニーズに甘えていてよいのかは疑問である。もっと塾教育を多様性に富んだものにできないだろうか。教育改革への積極的発言を通じて、塾が改革の主役となるべきではないか。もちろん、改革が成功すれば塾へのニーズは消滅する。われわれの経営は成り立たなくなる可能性がでてくる。しかし、そのような目先の利益にとらわれることなく、日本の教育政策を根本から変える案を用意すればよい。すなわち、塾が学校となるような改革案である。オランダでは、300人の生徒を集めれば私立学校の設立が可能である。そこでは公立、私立を問わず生徒一人当たり同額の予算が生徒の人数に応じて国家から支給される。その予算内で各学校は工夫した特色あるすばらしい教育を行っている。だから、家庭の経済状態により教育格差の生じる余地がない。このような受験競争にとらわれない教育を夢見ることはどうだろうか。
〔注〕中曽根臨教審が発足した1984年に当時の大蔵省が中心となって学者や若手官僚を集めて「ソフトノミックス・シリーズ(全37巻)」を発刊した。それは、いまやこれまでのハードな社会からソフトな社会(サービスや情報を重視する社会)へ移行する転換点にあると位置づけ、そのためには経済の自由化と競争原理の導入、ならびに財政的に小さな政府を志向するために、あらゆる分野の検証とこれからの予測をおこなったシリーズである。「隙間教育産業」という言葉は、このシリーズの第7巻『第1部 構造変化の分析ー7 《ソフト化社会の家庭・文化・教育》』の中で用いられている。
4.次に、経済的弱者との関わりについてである。
塾が有料であるということは、それもかなり高額であるゆえに、家庭の経済力によほど余裕がなければ通塾は不可能である。そういう意味では、塾の門戸は家庭の経済力如何により選別されているわけであり、家庭に経済力のある子どもだけを教育しているということになる。これは、民間企業全てに当てはまる市場主義経済から生じる結果であり、致し方ないことである。
ただ、そのことがいま学校現場で生じている学力格差(学力の2極化、いや、3極化以上かも知れない)を、ますます助長させる一因を作っているのではとの危惧が生じる。それも市場原理ということだけで切り捨てられるものだろうか。教育という言葉が虚ろに響いてくるのを禁じえない。
バブル期にはかなりの生徒が塾に集まっており、どの塾も入塾テストを行い選別を行っていた。特に大手塾や進学塾を標榜する塾はそうであった。しかし、少子化の進行と経済の悪化ならびに塾業界への新規参入者の増加などにより、生徒の奪い合いが激しくなり、いまや入塾テストを行うケースは皆無といってよい。
そうした中で、以前なら塾に通っていた成績下位層の塾通いがめっきり減ってきている。塾生たちからは、学校での同じクラスのAもBもCも塾へ行っていないよ、というような情報が入ってきたりする。と同時に塾長仲間からも同様の声を聞くようになってきている。彼らはどこで誰に救われるのだろうか。
5.最後に、授業の内容ないしは教授法についてである。塾での最大の売りは、先ずは学校のテストの点数を上げることである。特に、中学校で年に4~5回行われる定期テストの順位を上げることは、塾の存続にも関わる重要な仕事である。一般の生徒はそのために塾に通っていると言ってよい。
では、どうやって成績をあげるかが問題である。特に、部活付けで普段勉強していない生徒の場合は問題である。一朝一夕で成績が上がるはずはないからである。それでも塾としては順位を上げてやらなければ親からクレームがつく。だからテスト前5日間の部活休みが勝負ということになる。
このような場合にほとんどの塾でとられるテスト勉強法がる。それが「ごまかし」勉強である(藤澤伸介著『ごまかし勉強〈上〉学力低下を助長するシステム』新曜社を参照)。
藤澤氏は、「ごまかし」勉強の中身を「学習範囲の限定」、「代用主義 」、「機械的暗記志向(暗記主義)」、「単純反復志向(物量主義)」、「過程の軽視傾向(結果主義)」の6つに分類されているが、なるほど指摘されてみると納得すると同時に、耳の痛い指摘である。
この中で最も問題なのが「学習範囲の限定」であろう。実はこれは塾の責任ではなく、学校の責任である。試験2週間前になると範囲表なるものが配られる。そして、丁寧にも更なる範囲の限定や出題されそうな要点や問題までプリントで配布される。これでは、傾向と対策をプロとする塾側にとっては、それに乗らない理由はないし、というよりは生徒たちの方がそれ以上のことはやろうとしない。かくて、要領のよい生徒が上位を占め、推薦で高大へと進学できるサイクルが出来上がることになる。
以上のような実態の中で、われわれは学力をどう捉えたらいいのだろうか。ニーズ論に従えばこれで良しと言うことになろうが、それでは日本の子どもたちの学力低下を云々する資格はないのではないか。よく塾長たちの間から「日本の子どもたちの学力は塾が支えている」という声を聞くことがある。しかし、官民挙げての「ごまかし」勉強の下では、本当の学力は望めないのではないか。
これを脱却するには、藤澤氏が提唱されるような「正統派学習」、すなわち「学習範囲の拡大」、「独創思考」、「意味理解志向」、「方略志向」、「思考過程の重視」という方向を目指すべきである。もっとも「学習範囲の拡大」は学校側の権限であるが、それの持つ害悪の側面を塾側が強く学校側や生徒たちに指摘するのも一つ仕事とかんがえたい(ただし、学習範囲の拡大は、通塾率をあげることになるとの反論も予想されるが、本当の学力の向上のためには必要なことである)。
六.日本の教育をよりよくするに(一つの提言)
以上をまとめると、現在の公教育の問題点は、学力競争→公立学校への不安→学習塾(予備校)通い→私立受験→公立学校の地盤沈下、という悪循環に陥っていることである。これを断ち切る方策こそが教育改革の決め手となる。したがって、以下の3点を提言したい。
1.行過ぎた進学(受験)競争を止めるためには、その頂点に位置する現在の大学入学資格を現在の入学試験制度からOECD諸国が採用している「高校(中等教育)卒業資格認定試験」へ移行させ、その資格を有する者はいつでも、どこの大学にも進学できるようにする。
2.教育に家庭の格差を持ち込ませないために、就学前教育から小中高までの教育を公立学校と私立学校とを問わず授業料を無償とし、その代わり生徒の数に応じた一定額を公費負担として保障する(財政平等の原則の確立→オランダ、フィンランドの教育参照)。
それにより、憲法一四条の平等原則が貫徹され、社会や家庭内の格差が教育の格差に及ぼす影響を排除できる。
3.現行の指導要領のような規制をもっと緩和し、かつ教科書検定制度を緩め、各学校の教育の自由の幅を広くして、真に自由な特色ある多様な教育を行えるようにし、また学校選択の自由を保障する。
3.子どもの数が300人以上集まれば、一定の要件の下で誰でもが私立学校の設立が可能なるようにする(→オランダの教育)。これにより学習塾も私立学校として参入が可能となり、公立と私立の特色ある多様性に富んだ内容の学校の出現が期待され、いい意味での競争が行われることになる。
《終わりに》
塾を初めとする民間教育(私教育)産業は、教育の論理ではなく、経済ないしは産業の論理で動いている(その証拠の一つが、学習塾関連の全国組織である社団法人「日本学習塾協会」や学習塾協同組合は、経済産業省の管轄下にあることだ)。にもかかわらず、教育という一つの言葉で括られることが多いということが、わが国の教育を論じる場合に曖昧さや混乱を招いている。それは、通常において教育を話題にする場合には、公教育も塾のような私教育も一緒の範疇であるのに対し、教育改革を問題にする場合にはそこでの教育には塾などの民間教育産業はすっぽりと抜けてしまっているからである。もし塾などの民間教育産業を公教育と並存するものとして容認するのであれば(世論もマスコミも勿論のこと、行政までもが容認している雰囲気がある)、公教育の分野のみを改革の対象とするのではなく、民間教育産業の分野も対象に含めないと、実りある成果は生み出せないし、また公教育の方はいろいろな法的規制をかけながら、他方は野放しで自由というのでは均衡がとれないのではないか。そこにメスをいれないということは、行政(特に文科省)としては建前上塾などの民間教育産業は公教育の外に勝手に存在しているものであり、何ら公教育と関わるところはないと装っているにほかならないからだろう。しかし、このような行政の態度は、これほどまでに学校現場外で民間教育産業の影響力が大きくなっていることとますます乖離し、公教育の縮小化とその実質的な民営化への道を開くことになるのではないだろうか。このような公教育を民営化するという確固とした理念があり、それを国民に説明するのであればそれも一つの選択であろうが、なし崩し的にそれが行われてゆくのは極めて危険なことである。
去る3月11日の大震災と東京電力福島原子力発電所の事故は、これまでのあらゆる価値観の再考を迫っているように思われる。そこで最も問われているのがわれわれの「幸せと何か」ということである。われわれはあまりにも物質的のもに比重を置いてきたのではないか。それがあくなき経済成長路線を推し進めてきたと言えよう。地球に優しいという表現は間違っているが、地球に負荷をかけない生活を目指そうという思想は歓迎されるべきである。そして、このことの実現の鍵は教育にこそかかっていると思う。そういう意味においても、われわれ塾人も教育の一端を担うものとして、日本の教育をよりよい方へと導く流れの原動力に加わりたいものである。
[ 2011/7/29 記]