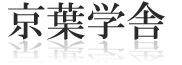去る2005年3月31日の活字議連の総会で、次のようなやり取りが議員の間で行われた。
「公立の図書館がない市町村もある。法律を作ることで、どういう施策を推し進められるのか。国民全体で活字文化を大事にしよう」(前文科大臣・河村健夫氏)
「年末に発表されたOECDの調査結果は衝撃的なニュースであった。文字文化、活字文化、読解力、表現力は人間としての基本だ」(鈴木恒夫氏=自民)
「日本の将来を危ぶむ声の多いのは、活字文化への危機感と表裏一体だ」(山岡賢次氏=民主)
ここからもわかるとおり、議員たちの心理には巷に流布されている国民の活字離れといわれている事態に対する漠然とした危機感と、OECDの国際学力到達度調査(PISA)結果で読解力が14位に下がったという具体的な事実からくる切迫感とが混合している。しかも、これが加速すると日本文化の衰退を招き、さらには、ここが特に保守の側から強調されるところであるが、文化と「伝統」は表裏一体の関係にあり、伝統が忘れ去られてしまうかもしれないという、まさに日本のアイデンティティの危機という認識も影響しているようだ。
とはいえ、日ごろの議員たちの活動をみていると、こういう認識が沸々と湧いてくるとは一般的には考えにくい。やはり、背後に仕掛け人がいるはずである。
その仕掛け人こそ02年10月に結成された「活字文化推進会議」(事務局 読売新聞社内)という団体である。国民の活字離れを懸念し、それを防ぐための具体策の必要性を説いている。その音頭をとっているのが読売新聞社であり、他の出版業界や作家、知識人らに呼びかけて会の結成にこぎつけたという次第(どういうわけか、朝日、毎日など他紙はこの法案についての記事をほとんど取上げてこなかったが、そのわけがここらにあったのでは?)。
活字離れは何も書物に限られたことではなく、新聞も同様である。アメリカから日本にも伝わってきたNIE(Newspaper In Education)運動も、市民の新聞離れを防ぐためには、小中高生のときから新聞に親しんでもらうという新聞業界の思惑がある。出版業界も全く同様である。そして、活字離れが読解力の低下と結びつけられると、ストレートに教育問題となる。本法案の基本理念の中に「学校教育においては、読む力及び書く力並びにこれらの力を基礎とする言語に関する能力(=言語能力)の涵養に十分配慮されなければならない」とあるのは、このことを具現しているといってよい。
このようにみてくると、本法案の狙いが文字・活字文化の振興という普遍的で崇高な目的と理念を有しながら、他方では新聞を含めた出版業界の振興という思惑をも有していることを否定できない。もちろん、文字・活字文化の振興には出版業界の振興も必要であろうことは理解できるし、原則論としては正しい。しかし、法案の中身によっては、後者が一人歩きをはじめ、前者は単なる理念に終わってしまう(たとえば、財政の裏づけがなされないといった具合に)という虞がないとはいえない
中学・高校・大学受験、補習、公立中高一貫校の適性検査、国語対策、時事問題対策などに定評のある塾